【風のたより(6)】 by
銀の星
・第26回~第30回まで('05/09/13~06/05/15)
第30回(2006/05/15)
前回の3月から、ついこの間のゴールデンウィークまで、北海道は寒くて寒くて寒くて……。
冬が寒い、というのとはまた違い、延々と春が来るのが遅れている!という感じで、すごくいやだったのですが、よぉーやく、先週から温かくなりました。桜の花もようやく咲いて…。
と、思ったら、今日なんかは、もう初夏の陽気!あったかいのは大歓迎だけれど、ちょっと早すぎ!それでいて、夕方からはすごくヒンヤリするので、一体何を着たらいいのかわからない!ホントに、ちょっとムッとします。
こんな風に、気候に揉まれているので、なんだか疲れ気味…。絵も写真もなくてごめんなさい。本当の近況のみ。近々、また遠出する予定なので、その時は何か載せますね。多謝。
第29回(2006/03/02)
※この回の内容・〔里見の弟子は困りもの? ─芥川龍之介に抱きついた男・中戸川吉二─〕は、当HP〈緑の木もれ陽〉(エピソード集)の〈里見弴 Episode-2〉に収録いたしました。
第28回(2005/12/20)
※この回の内容は、当HP〈緑の木もれ陽〉(エピソード集)の〈有島生馬 Episode-1〉として再Upいたしました。注釈もつけ加えましたので、どうかご覧下さい。
 湖のそばの、こぢんまりした三角の山。まるで神さまが富士山を模して造った、可愛い箱庭みたいな…。
湖のそばの、こぢんまりした三角の山。まるで神さまが富士山を模して造った、可愛い箱庭みたいな…。
そう、ご存じの方も多いと思いますが、これが榛名山。ふもとに広がる湖は、榛名湖です。
画家の竹久夢二(明治17・1884年生まれ)は、昭和5年(1930)、榛名湖のほとりに小さなアトリエを建てました(写真2枚目)。
それは、単に彼の創作のためだけに建てられたものではありませんでした。〈榛名山産業美術研究所〉。彼は、自然に囲まれた落ち着いた環境の中で、様々なアーティストたちが集い、生活に密着した美術工芸──例えば草木染や木工芸、織物や手漉和紙など──が研究できる場所を創ることを夢みていました。小さなアトリエは、その記念すべき第一歩となるはずでした。
 そして彼は、その夢をもっと確かなものにするべく、外国で展覧会を開くなどして資金を集めようと、翌年に渡米したのです。
そして彼は、その夢をもっと確かなものにするべく、外国で展覧会を開くなどして資金を集めようと、翌年に渡米したのです。
ところが、展覧会は空振りの大不振におわりました。ちょうど折悪しく、当時、アメリカは大恐慌のまっただ中(1929年から)。それに、アメリカ人の間に、力をつけはじめた日系移民への反感が高まりつつあったという情勢も、夢二には災いしたのでしょう。失意の上に、すっかり健康を害した夢二は、結局、帰国してまもなく入院生活。二度とふたたび榛名に戻ることなく、昭和9年(1934)に満49歳で世を去ったのです。アメリカで描いた「青山河」という作品の裏に彼は、「山は歩いて来ない。やがて私は帰るだらう。榛名山に寄す」と記していたのですが……。
 でも、夢のかけらは残しておくもの。夢二がたびたび訪れていた伊香保周辺には、彼の作品を集める熱心なコレクターや研究者、そして伊香保温泉の人々などが、夢二の死後も彼をなつかしみ、慕い続けました。やがて昭和56年(1981)、6年以上の構想期間を経て、竹久夢二伊香保記念館がオープン(写真3枚目)。数多くの夢二作品が、常時展示されるようになりました。また、平成6年(1994)には、榛名湖のほとりの夢二のアトリエも、当時の記憶や写真をもとに再現され、誰もが訪れて見ることが出来るようになりました。
でも、夢のかけらは残しておくもの。夢二がたびたび訪れていた伊香保周辺には、彼の作品を集める熱心なコレクターや研究者、そして伊香保温泉の人々などが、夢二の死後も彼をなつかしみ、慕い続けました。やがて昭和56年(1981)、6年以上の構想期間を経て、竹久夢二伊香保記念館がオープン(写真3枚目)。数多くの夢二作品が、常時展示されるようになりました。また、平成6年(1994)には、榛名湖のほとりの夢二のアトリエも、当時の記憶や写真をもとに再現され、誰もが訪れて見ることが出来るようになりました。
今、夢二記念館は本館のとなりに新館が併設され、さらに別棟として〈音のテーマ館〉(オルゴール館)や〈義山楼(ぎやまんろう)〉(ガラス工芸)の2館が開かれています。夢二作品だけではなく、夢二の産業美術研究所構想にちなんで、大正から昭和初期のレトロモダンな美術工芸品を出来るだけ集める、という方針のようです。ホールには大正時代のピアノが置いてあったり、館内の照明もランプシェードが大正期のものだったり…。私は、夢二の生家のある岡山の方には行ったことはありませんが、この伊香保の、夢二にかける意気込みの熱っぽさは、岡山に決して勝るとも劣らないのではないでしょうか?
* * * * * * * *
さて、そうした夢二の〈産業美術〉の夢に魅かれて、その死後も彼の夢のかけらを大事にしていた男が、ここにも一人。そう、それが『白樺』出身の画家・作家にして有島三兄弟の一人、有島生馬(いくま、本名・壬生馬(みぶま))でした(明治15・1882年生まれ)。
彼こそ、夢二が榛名湖畔に美術研究所を建てるにあたって協力を惜しまなかった、心の友だったのです。
もともと、夢二と『白樺』とは、浅からぬ縁がありました。まず、『白樺』を発行した出版社〈洛陽堂〉ですが、夢二もこの洛陽堂から、『白樺』創刊前年の明治42年(1909)12月に、最初の著書『夢二画集 春の巻』を刊行しています。(一説によると、洛陽堂が本を出版したのもこれがほとんど初めで、当時の店主が、夢二の絵のふんわり華やかな雰囲気にちなんで、自分の社名を「洛陽堂」としたのだとか…。)
ちょっとアンニュイで、たおやかな感じの夢二の絵は、当時の女の子たちの心をつかまえて、売れ行き絶好調。翌43年には『春の巻』の続刊の夏・秋・冬の巻や、『月刊夢二カード』(絵ハガキ集)なども続々刊行されました。『白樺』も後には人気雑誌となりましたが、当初、売れ行きがどうなるかわからないこの同人雑誌を洛陽堂が出し続けてくれたのは、経営面で、この夢二人気の支えがあったからなのです。
一方、夢二にとっても、同発行所で出している『白樺』は気になる雑誌だったことでしょう。毎回さまざまな西洋美術を紹介してくれるだけでなく、その同人や仲間には、有島壬生馬や南薫造といった洋行帰りの新進画家がいるらしい…などと思い、同世代の芸術青年としては興味津々だったに違いありません。そして、白樺主催の展覧会があればかけつけていたらしいことは、明治44年(1911)10月の泰西版画展覧会の時など、「第一の入場者は竹久夢二君で、十一日の午前七時四十分だつた。開場時間より二十分早く来て下さつたわけだつた」(『白樺』明治44年11月 署名・記者)と書かれていることからもうかがえます。
また、夢二は、『白樺』に紹介されていたハインリッヒ・フォーゲラーという画家からも大きな影響を受けました(最初の紹介は明治44年12月)。フォーゲラーの描く繊細な女性像もさることながら、自然を愛し、芸術と人々の生活が融合する穏やかな理想郷を目指す彼の姿勢に、深く感銘を受けたようです。事実、フォーゲラーは、ドイツのヴォルプスヴェーデで、自分の信念にもとづいた芸術家コロニーを実行に移していた人(1894~1930年まで)。また、短い期間ですが、『白樺』同人とも手紙で交流をしていました(明治44年・1911~大正2年・1913 主に手紙を書いていたのは柳宗悦)。
フォーゲラーの思想からインスパイアされて、夢二も後に芸術家コロニーを作ることを夢みて……その“ユートピア建設”への志向は、武者小路の〈新しき村〉とも響き合っていて……その夢二に協力し、理想実現への希望を与えていたのが有島生馬で……と見てゆくと、意外な反面、どこか納得のできるつながりという気がします。
夢二がいつ生馬と友だち同士になったのかは、具体的に書かれた資料が少ないので、今のところはわかりません。しかし、生馬と夢二の絆がいかに深いものだったかは、生馬が、芸術界に理解者が少なかった夢二を、フランスの詩人・ミュッセになぞらえて〈孤独と寂寥の詩人〉と呼び、賛辞を贈ったこと(生馬「悲しき影の夢二」大正七年)や、関東大震災以来人気が落ちて沈み勝ちだった夢二を、いつもそばで支えていたことなどからもよくわかります。夢二を元気づけるため、たびたび伊香保や草津の温泉に連れ出していたのも生馬でした。また彼は、夢二が亡くなった時、墓地に彼の碑を建てて、〈竹久夢二を埋む〉の文字を揮毫しています。その翌年には、榛名湖畔に夢二の歌碑を建てる計画の代表者にもなっています。夢二亡きあとも、生馬はずっと彼のよき友だちでした。
官展系の主流派に抗して二科会(大正3・1914)・一水会(昭和11・1936)などの新興の画会を次々形成し、日本洋画壇をリードし続けた人(後に文化功労賞受賞)として堅いイメージが先行しがちな有島生馬ですが、彼にはこうした一面があったのです。
しかし、そういう生馬の行動を、不可解に思う周囲の人もいたようです。特に志賀直哉は、“本来芸術家であるべき生馬が、生活の方を大事にして、竹久夢二の絵などに惚れ込んで芸の道を捨ててしまった”と否定的に考え、それが60歳過ぎての生馬との絶交の一因となりました。「(生馬は)芸術を信じないで芸術家といふ額縁にをさまつてゐる事が困るのだ。君は金持ちといふ額縁にをさまつてゐれば一番似合ふ人だ。(中略)夢二好きで、その蒐集をしてゐるとでも云へば却つて好感が持てる位である」(志賀「蝕まれた友情」昭和22・1947年)。
そもそも、夢二の活躍フィールドは、イラストに詩に作詞、油絵、日本画、それに版画、工芸デザインや服飾デザイン、本の装幀から人形作りまで、あまりにも多彩。現代ならばマルチアーティストとして一躍脚光を浴びるところでしょうが、当時はサブカルチャーという言葉さえなかった時代。〈芸術〉と〈大衆性〉とは完全に対立する概念だと考えられていましたから、ある意味、志賀が夢二の価値を認めなかったとしても、無理はありません。それどころか、実はごく最近まで、夢二は、いわゆる日本美術史の中に居場所がなかった人なのです。
 でも、時の流れが答えを出してくれることはあるもの。もう、今や、志賀と生馬の絶交のいきさつを憶えている人はほとんどいないでしょうが、それとは関係なく、夢二の絵は時代を越えて思い出され、愛され、その洗練されたモダンさが見直されています。夢二のきものや半襟のデザインの斬新さは、現代のカジュアルきものブームの源流ともなっています。何より、もう100年も経って、美意識も価値観もすっかり変わってしまったはずなのに、いまだに、夢二デザインのハンカチや小物を「すてき~」「可愛い!」と手にとる女性たちが後をたたない、ということは、考えてみればものすごいこと。誰にも出来るということではありません。
でも、時の流れが答えを出してくれることはあるもの。もう、今や、志賀と生馬の絶交のいきさつを憶えている人はほとんどいないでしょうが、それとは関係なく、夢二の絵は時代を越えて思い出され、愛され、その洗練されたモダンさが見直されています。夢二のきものや半襟のデザインの斬新さは、現代のカジュアルきものブームの源流ともなっています。何より、もう100年も経って、美意識も価値観もすっかり変わってしまったはずなのに、いまだに、夢二デザインのハンカチや小物を「すてき~」「可愛い!」と手にとる女性たちが後をたたない、ということは、考えてみればものすごいこと。誰にも出来るということではありません。
大正・昭和期に画壇で活躍した人たちは多けれど、みんなだんだん影が薄くなって、今でも人々の心に生きている画家はほんの一握り。おそらく、志賀直哉が“これぞ日本の芸術家”と考えていた人たちにしても、例外ではないでしょう。そこへゆくと、竹久夢二の作品は、芸術家として、そして優れたデザイナーとして、人々に豊かなイマジネーションを与える可能性をまだまだ秘めているのですから……。やはりこのことに関しては、生馬の勝ち!といえましょう。
白樺派の〈十人十色〉、自分の好きなものは友だちがどう言おうと好きなんだ、という信念の強さやマイペースさは、こんなところでもいかんなく発揮されているのですね。
第27回(2005/11/25)
北海道はもうすでに雪のシーズンですが、札幌近郊では積もっては溶け、積もっては溶けで、今は晩秋に逆戻り。あんまり、ホワイトクリスマスを予感させる景色ではありません。
 でも、札幌の大通には一足早くクリスマスの賑わいが…。この、あふれんばかりのクリスマスカラーの華やかさ!
でも、札幌の大通には一足早くクリスマスの賑わいが…。この、あふれんばかりのクリスマスカラーの華やかさ!
そうです。これは、恒例の〈ミュンヘンクリスマス市〉。ミュンヘン市と姉妹提携を結んでいる札幌で、数年前から行われているこの企画。ドイツからの工芸品のほか、本場のお菓子やホットアップルワインなども店にならんでいて、気分はドイツの“ヴァイナフテン”(聖夜)!
ずいぶん昔になりますが、3ヶ月ほど、ミュンヘンに住んでいたことがあるんです。そのときは春から夏にかけてだったので、クリスマスは経験できませんでしたが…。だから、出店の中にいるドイツの方たちを見ると、とてもなつかしい気持ちになります。
この催しは12月11日まで。こちらまでおでかけになれる方には、ちょっとでも覗いてごらんになることをおすすめします。たしか、夜8時か9時頃までは開いていますし、ホワイトイルミネーションも始まっていますから、夜の景色もまた素敵です。12月に入ると、多分雪景色になるでしょうから、そうなるとクリスマス気分もひとしおですよ。
さて、私は、明日から群馬県の方へ行ってまいりま~す。
番外(2005/11/23)
★ごぶさたしておりました。
仕事上で、割合大きなプロジェクトに参加して1年余り。先日、ようやく一段落つきました。
でも、…後味ははっきり言って、あまり良くありません。
こんなところで皆さんに愚痴をこぼすのはお門違い、とは知りつつも、あえて最近考えたことを一つ。
〈文学〉に関わる人(研究者・オールドファン・または創作者の方々)は、よく、 「文学は後世に伝えていかなくてはならない大事な文化です」「だからもっと、一般の方々にも読んでほしい、興味を持ってほしい」「若い人も気軽に読書を」などと言う。
ところが、いざ、仕事や事業となると、論調ががらりと変わる。
「お役人(ここでは公務員のこと)なんかに何がわかる」「企業なんかが文学に手をつけようとしたって、一朝一夕にどうにもなるもんでない」「ずぶの素人にわかりっこない」と。でもこれは、先の発言とかなり矛盾しているのでは?
要するに、自分たちは文芸や芸術がわかる〈文化人〉側の人間であり、それ以外は素人であり俗人であると。「いや、そんな事は言っていない!」とおっしゃるのかもしれませんが、では、どういう風に解釈したらいいんでしょう?
ちなみに、上の人たちが口をきわめて軽蔑する具体的な「お役人」のうち、私がよく知っている一人は、もともと吹奏楽をやっていた人で、ピアノも素敵に弾けますし、奥さんもお子さんも音楽大好きの音楽一家。もう一人は茶道をずっとやっていて、最近、教授者の資格をとったばかり(男性)。
「お役人」といったって、お役人の木に成るわけじゃなし。企業人やビジネスマンにしたって、同じですよね。人にはそれぞれの人生あり。確かに文学の専門家ではないかも知れませんが、身につけている特技や、知識や、感受性の豊かさでいえば、自称ブンガクシャとどっちが優れているかなんて、にわかには言いかねると思うのですが。第一、優劣をつける問題でしょうか?
* * * * * * * *
それから、耳にしたのが、「〈北海道文学〉の素晴らしさを、もっと声を大にして、世の中の人に知らしめねばならない」という言葉。
ところがその同じ場所で、「〈北海道文学〉の本当の良さは、北海道の人間にしかわからない」という発言も出る。そして、互いにケンカもしなければ論争もしない。当然の事を言っているような顔をしている。でもそれって、矛盾じゃないのだろうか。それとも、“良さはどうせわかるはずはないが、素晴らしさだけは認めてほしい”ってこと?
そのくせ、そういう人たちが〈北海道文学の父〉として尊敬している人物が、有島武郎なのですから。…今さらの話ですが、有島武郎は横浜生まれで、血統は薩摩人。北海道を舞台にしたインパクトの強い小説を何本か書いたのは事実ですが、じゃあ、有島だけは、先の基準に照らして言えば、別格ということですか。まさか、〈本当の良さ〉も何もわからないで、〈北海道文学〉なるものを書いた、と言いたいわけではありませんよね?
* * * * * * * *
そんなこんなで、気分がクサクサした時に、『白樺』の人たちのものを読むと何となくせいせいします。
もちろんそれは、私がたまたま白樺派の作品が好きだからで、だれでも、価値観のおおらかな人の書き物を読むと気持ちが晴れ晴れするのでしょうけれど。
一つ言えることは、小説家の武者小路でも志賀でも里見でも、他の分野に進んだ人でも、あの人たちは“最初から理解する気もなくて人を軽蔑しているような奴らにわかってもらうつもりはないよ”とは明言していても、はじめから“あんな奴らには文学(芸術)がわかるはずがない”なんて決めつけたことはない、ということです。
要は、“わからず屋はきらいだよ”と言っているだけであって、身分とか、立場とか、職業とか、出身地とか、さしあたってその人の努力ですぐには変えられない事柄を理由にして自分と差別化はしなかった、ってことです。その点、小気味いいほどきっぱりしている。
以上、私感で恐縮ですが、最近の心のモヤモヤにようやく整理がつきましたので、ここに記した次第です。
第26回(2005/09/13)
今年は、少しおそい夏休みをとって、8月の末に洞爺湖からニセコまで、2泊3日で温泉めぐりの旅に行ってきました。
出発の前の夜には、ものすごい集中豪雨で、行った先はどうなっているだろう、と不安でしたが、その後は晴れ続き!洞爺湖も、多少は水かさが増していましたが、空の青さを映して、ガラス細工のようなブルーグリーンに輝いていました。
今年の北海道は夏が長く、9月になっても暑いくらいです。この時も、まるで真夏のような暑さで、打ちよせる湖の水が気持ちよさそう…。
 実は、今から96年前の明治42年(1909)、季節も同じころ、当時満21歳だった里見
弓享が洞爺湖を訪れていました。
実は、今から96年前の明治42年(1909)、季節も同じころ、当時満21歳だった里見
弓享が洞爺湖を訪れていました。
父・武や兄・武郎と一緒に狩太(ニセコ)の農場に来ていた英夫(里見)と弟の行郎(ゆきお)。しかし、父と兄は何か調査でもあるのか、毎日毎日、広大な農場を見回ってばかり。彼と弟とは、“駄菓子屋一軒ない僻地”で時間をもてあましていたといいます。
そこで、兄の武郎がすすめてくれたのが、洞爺行きでした。弟と2人、馬にまたがり、朝の7時に出発。それから午後3時まで、途中一休みしたとはいえ、丸8時間かけてたどりついたとのこと。今なら、ローカルバスを乗り継いだとしても1時間半くらい、ドライブなら1時間前後で着ける距離なのですが…。
でも、少しくらい時間はかかっても、未開拓の異境を馬で歩くなんて、滅多に経験できることではありません。そこで里見は、同年9月の回覧雑誌『麥(むぎ)』に、この洞爺行きの事を紀行文にまとめて掲載しています。
で、本当をいうと、私が今回、夏の旅に洞爺─ニセコのルートを選んだのも、この文章を読んで、里見 弓享が移動した空間を知ってみたくなったからなのです。
(上の写真は、洞爺湖温泉の宿から、湖中心部の中島を撮したもの。この写真には写っていませんが、対岸の左手側に、里見が泊まった向洞爺(むかいとうや)の町があります。)
里見 弓享のこの「洞爺行」は、小品ながら、人跡まばらな留寿都(ルスツ)から向洞爺までの山道の雰囲気や、湖畔に小さな集落しかなかった当時の洞爺湖の様子をよく描き出していて、秀逸です。いつかは、作品全体をご紹介したいと思っています。
ただ、それはさておくとして、注目したいのは、作中の湖にまつわる文章。「夕方一つ游(およ)いで見やうと云ふ事になつて宿の手拭を借りて(荷が来ないから)はいつた。水は湖にしては驚く許(ばか)り温(ぬる)い。特に不凍湖だとも云ふから少し温泉の気味なのだらうと思ふ」。里見は、水の温かさで、ここが温泉のわき出すところだという事を直感していたのですね。現に今、洞爺湖温泉街には足湯が6ヶ所、手湯が13ヶ所もあって、その数は道内ナンバーワン!手湯足湯のスタンプラリーもありますし、試しにホテル前の手湯に手をひたしてみたら、あったか~い!ほんのちょっとの間、手を入れていただけなのに、フワ~っと全身あたたまったような感じがしました。里見
弓享の時代にも至る所にこんな湯どころがあったら、ずいぶん楽しめたでしょうに。
(付記: その後旅行ガイド等を見ましたら、現在の“洞爺湖温泉”の湯は明治43年(1910)の──里見のこの旅の翌年、『白樺』創刊の年の──有珠山噴火によって噴出したもので、しかも、人々に発見されたのは大正6年(1917)になってからだったとのことです。そして、この噴火以前には、このあたりに一般に認められるような温泉の湧出はなかったというのです。
だとすると、まだ周囲にまったく温泉の気配もない時期に、たまたま泳ごうと体をひたした湖の水がぬるかったというだけで、すぐに〈温泉〉にまで連想がとんだなんて……さすがは里見、感覚&直感がするどい! (2005/09/20))
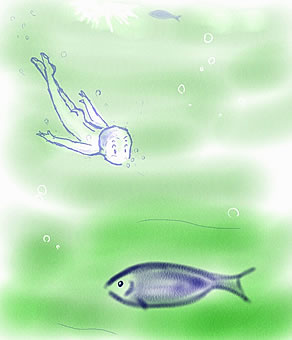 そして、弟と湖に入った里見は、ずっと泳いで沖の方へ…。
そして、弟と湖に入った里見は、ずっと泳いで沖の方へ…。
「沖に出て下を見ると真青(まっさお)で底が見えない。美麗(きれい)な透明な水なのだから大概なら見える筈なのだ」。澄み渡った透明な水なのに、底がまったく見えないというのは、もの凄いほどの神秘感だったでしょう。里見がここに来る以前にも、ある人が深さを測ってみたくなり、おもりをつけて糸を下ろしてみたものの、下ろしても下ろしても一向に手応えがないので、ついに恐ろしくなって、糸を放り出したまま岸に漕ぎ帰ってしまったそうです。確かに、火山の爆発で出来たカルデラ湖の洞爺湖は、最深部が179m!普通の糸玉やロープくらいで測れたはずはありません。里見もやっぱり、「この湖にハ底の知れない処があると云ふ事を聞いて居たから気味が悪くなって直(すぐ)に岸に帰つた」ということです。
でも、それにしても、まだ温泉街もなく、湖岸の集落もほんの小さなものがあるばかりという時代に、裸で洞爺湖を泳ぎまわることが出来たなんて……。もう、今なら絶対どこでも経験することが出来ないような(なぜなら、現代では“無人境”というのもたいていは演出ですから)、文字通り、大自然のふところに抱かれる体験だったわけですね。水から上がったあとは、「まつ裸で宿の前の桟橋の上に立つて夕日を浴び心持はよかつた」とのこと。堂々たる自然児の風貌です。何だかとても、うらやましい気がしました。